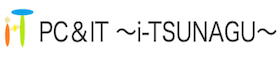パソコンの初期設定で行うべきこと。PC初回セットアップ手順。
※当サイトには広告やプロモーションが含まれています。

さて、新しくパソコンを購入したら使用できる状態にセットアップしてあげる必要があります。
通常は、電源を入れた段階で自動で設定が開始されたり、初期セットアップ用のウィザードが立ち上がってきます。
初期セットアップウィザードでは、画面の指示に従って入力していくとコンピュータ名やユーザー名、アカウント、国や言語、時刻などが設定できます。
この作業は難しくないですし、時間的にもそこまでかからずに完了することができると思います。
ただ、この作業が終わった段階(初期セットアップ用のウィザードの完了など)でパソコンを操作したりすることは可能になるので「セットアップ完了」と満足してしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、実際は他にやるべき作業や、しておいた方がよい作業がいくつかあるのです。
そして、やるべきことをやっておかなかったり、よくない順番で進めてしまうと後々問題となる可能性がありますので以下を参考にしっかりやっておきましょう。
今回は主に Windows のパソコンの場合を想定していますが、Mac の場合でも行うべきことのチェックなどにはご利用いただけると思います。
また初期セットアップ用のウィザードなどは OS のバージョンなどにより異なる場合がございますので、こちらのページではセットアップ用のウィザード内での詳細な様子や設定、入力などについては言及しておりません。購入後から利用を開始するまでに行うおおまかな流れについての説明をさせていただいているページとなりますのでご了承ください。
目次
パソコンの初回セットアップ時にやるべきことや順番。
まずは、項目を順を追ってリストアップしておきます。
詳細な内容・手順は、ページの下部や、他ページで記載しています。
PC初期設定(初回セットアップ)の項目と順序など一覧。
1.機器などの準備。開梱、マウス、モニター、キーボードなどとの接続、配線など。
2.電源を入れ、表示される説明(ウィザード)に従い設定する。
3.リカバリーメディアの作成。(必要な場合)
4.ネットワーク、インターネットに接続する。
5.Windows Update の実行、設定。
6.セキュリティ対策ソフトのインストール。更新。
以降は順番はそこまで気にされなくて大丈夫ですし、不要なものなど実行しなくてもよい内容も含まれます。
・メール関係の設定。
・Microsoft Office などオフィス系ソフトのインストールや認証作業。
・Adobe Reader など一般的によく使うソフトのインストールや更新。
・ブラウザの追加や設定など。
・よく利用するアプリケーションソフトウェアやプログラムをスタートメニューやタスクバーに追加する。
・不要なプログラムを削除する、スタートアップから外す。
・データの移行や引き継ぎ。
・社内ネットワークに関する設定など。
・プリンタや複合機、NASなど周辺機器との接続や設定。
ここまでがいろいろな方に共通して必要となるであろうと思われる設定などです。
あとは会社や業種により必要となるソフトウェアのインストールや機器との接続などを行なっていきます。
1~6については以下で少し詳しく解説しています。
PC初期設定(初回セットアップ)項目ごとの解説や手順。
1.機器を準備する。
開梱したり、電源ケーブルを接続したりします。
モニターやマウス、キーボードなどを接続します。
2.電源を入れ、説明表示(ウィザード)に従い設定する。
電源を入れると自動で準備が行われた後、初期設定用のウィザードが立ち上がりますので、表示されている内容に従い進めていきます。
OSやOSのバージョンなどによって画面や手順が多少異なりますが、ライセンス条項への同意をしたり、アカウントの作成、ユーザー名や、コンピューター名、国や言語、時刻などを設定します。
注意点やアドバイスとして以下のような点があります。
・コンピューターの保護や更新の設定など設定を選べる箇所は基本的に「推奨設定を使用する」を選んでください。
また、この場合のみならず、他の項目の設定やアプリケーション上の設定などでも特に理由がない場合は推奨設定を利用するようにしましょう。
・ネットワークへの接続ならびにパスワードやPINに関しては、後ほど設定できますので、ここではスキップしても構いません。
・Windows 8.1 や Windows 10 のアカウントには、ローカルアカウントとMicrosoftアカウントがございます。
Microsoftアカウント でサインインすることで、Microsoftのクラウドストレージ OneDrive 等のサービスを利用できたり、Windows ストア からアプリを入手したりできるようになります。
あとで変更することも可能ですが、Microsoftアカウント を新規作成したりサインインしたりする場合はインターネット接続が必要になりますので、項目4のネットワークに接続を先に行なっておく必要があります。
3.リカバリーメディアの作成
リカバリーとは、パソコンの調子が悪くなって他の方法で復旧させるのが難しい場合や、コンピュータウィルスに感染した場合などにパソコンのハードディスクの一部やすべてを購入時に戻してあげることで再度利用できるようにする作業です。再セットアップとも呼ばれます。
リカバリーをする際に必要になるのがリカバリーメディアです。
購入時にリカバリーディスクが付属している場合と、付属していない場合があり、付属している場合はあらためて別途作成する必要はありません。
リカバリーディスクが付属していない場合は、ハードディスク内にリカバリー用の領域が準備されているのですがこちらに不具合が起きてしまった場合にはリカバリーをすることができなくなってしまいますので、別途作成しておいたほうが良いというわけです。
リカバリーメディア用に利用できる記録用メディアはメーカーや機種などにより異なりますが、DVD-R4枚程度やDVD-RとCD-Rの組み合わせなどが多く、USBフラッシュメモリなどが使える場合もあります。
リカバリーメディアの作成方法はメーカーや機種により異なり、すべてのプログラムの中に再セットアップメディア作成用のツールが準備されていたり、メーカー独自の管理用ツールの中に入っていたりします。
基本的には、付属の説明書(マニュアル)に記載があるはずですので確認してください。
初回セットアップを行う際にはマニュアルなどを確認して必要なメディアを準備しておきましょう。

また、Windows 8 以降では、USBフラッシュメモリーを利用して回復ドライブを作成することが出来ます。
そして作成した回復ドライブを利用してPCを初期化したり、システムイメージを復元したりすることが可能です。
回復ドライブの作成などについては以下のページでも記載させていただいております。
⇨ 回復ドライブを作成してPCが起動できない等のトラブルに備えよう。
4.ネットワーク、インターネットに接続する。
ネットワークおよびインターネットへの接続がまだの場合には、ここで接続します。
新しい事務所でインターネット回線の契約もしたばかりである場合には、インターネット接続の初期設定(事務所などの環境内でインターネットが利用できるようにする設定。モデムやルータの設定。)や Wi-Fi 、アクセスポイントの設定などは先に済ませておく必要がございます。
5.Windows Update の実行、設定。
次に、Windows Update を実行します。
Windows Update とは更新プログラムの適用に関する機能になります。
つまり、Windows をその時点での最新の状態にするということです。
他のソフトウェアやプログラムにも共通することですが、セキュリティの概念からも常に最新の状態に保つことが基本となります。
なぜ、最新の状態に更新する必要があるのかという点については以下に簡単に記載させていただきます。
◾️ Windows Update などを実行し、最新の状態にしておいたほうがよい理由
更新プログラムには、脅威や脆弱性に対するセキュリティパッチや他のプログラムとの互換やバグ等の問題に対する処置や修正などが含まれます。
最新の状態でないということは、脆弱性がそのままになっていたり、脅威への対応ができていない、即ち、そのデバイスには隙があり悪意のあるプログラムなどから攻撃を受けたりする危険性が高くなっている状態であるということになります。
特に購入したばかりのPCは、工場で梱包や出荷されてから初期セットアップを行うまでの間、更新されておらず脅威や脆弱性に対処するためのプログラムが適用されていないことになります。
また、機能的な改善についても同様です。
上記のような理由でインターネットに接続したら外部のWebサイトに接続したりデータのやり取りなど他の事を行ったりする前にまず Windows Updateを実行し最新の状態にしてあげる必要があるのです。
◾️ Windows Update に関するPC内の場所
Windows Update はOSやOSのバージョンなどにより開始や設定を行うためのPC上の場所が異なる場合がございます。
- Windows 10(Pro 20H2 19042.1237) ・・・「スタートメニュー」>「設定」>「更新とセキュリティ」>「Windows Update」
最初は、[更新プログラムのチェック]を行い、その後確認された更新プログラムをインストールします。
WIndows Update は状況によっては、かなり時間がかかる場合がありますが、エラーが表示されない限り数時間はキャンセルせずに続けてください。
更新プログラムのインストールが完了したら、Windows Update 内の各設定や「詳細オプション」から、今後の更新プログラムのインストール方法の設定を確認し必要があれば調整などを行います。
6.セキュリティ対策ソフトのインストール
次に、セキュリティ対策ソフトをインストールし有効化します。
セキュリティ対策ソフトも、いろいろなメーカーが開発しておりWindows 自体にも Windows ファイアウォール や Windows Defender といったセキュリティ機能もあります。
どのセキュリティ対策ソフトを使うかは、他のセキュリティ対策状況や自身や企業のセキュリティポリシーなどにもよると思いますが、インターネットに接続する以上、何の対策もなしというのは危険ですので遅くてもこのタイミングで有効にしてから次の作業段階へ進んでください。
またソフトによっては設定や更新が必要な場合がありますので、それぞれご確認・実行してください。
◾️ よく利用されているウィルス対策ソフト
その他の設定に関する参考ページなど
⇨ 不要なプログラムを削除したり、スタートアッププログラムから外す方法。
パソコンの初期設定についてのまとめ
いかがでしたでしょうか?簡単に初期設定と言っても結構やることがありますよね。
購入した店舗や業者さんに依頼する場合、業者さん側からみると、なかなかの作業量で時間もかかるので、ある程度費用が掛かるのもわかるのですが、逆に購入する方の立場では現在のパソコンの本体価格に対して「設定にこんなに費用がかかるのか」と思われる気持ちもわかります。
初期設定などを自分で行うかは、自分のPCに関する知識や慣れ、使える時間などを考慮して判断しましょう。
このページを見ていただいて「簡単だ」「出来そうだ」と思われる場合、ご自身の責任の元で自分で行われた方が経済的です。
「とてもじゃないが技術的・時間的に出来ない」「面倒くさい」等の理由で、もし業者などに依頼される場合には、良心的な業者を選び、本体価格だけでなくトータルの費用も考慮いただいた上でご検討いただくことをお勧めします。
また無事に、ある程度の初期セットアップが完了した時点で次はバックアップのことも考える必要がございます。
重要なデータを保存した際のデータバックアップも、もちろんですが初期設定でもいろいろと設定などを行い作業量が多かった場合などは特に、システムイメージのバックアップ等の機能でバックアップをとっておくと完全にリカバリーをかけるより効率的に復旧できる可能性が高くなります。
システムバックアップについては、以下のページでも記載させていただいておりますのでよろしければご参考になさってください。
⇨ システムイメージでPCを丸ごとバックアップするには。復元方法まで。
こちらのページは以上となります。ここまでお読みいただきありがとうございました。